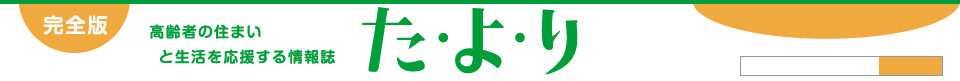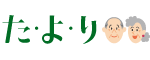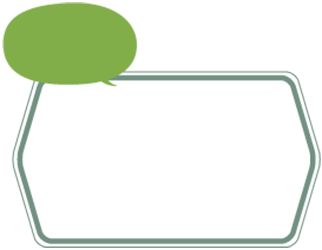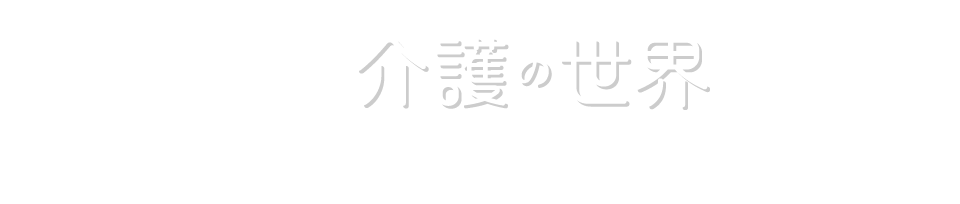
地域包括支援
センターへ
ズームイン
介護業界は、日々どのように変化しているのでしょうか。介護業界で
積極的な取り組みをされている方へズームアップして、お話しを伺いました。


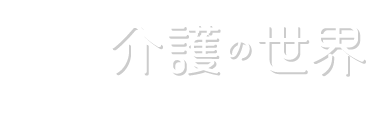
介護業界は、日々どのように変化しているのでしょうか。介護業界で積極的な取り組みをされている方へズームアップして、お話しを伺いました。
地域包括支援
センターへ
ズームイン

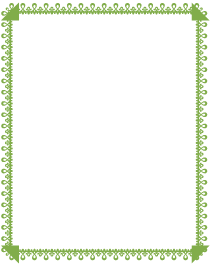
熊本県地域包括・
在宅介護支援センター協議会
会長 鴻江 圭子さん
高齢者の僧加と多様化を視野に地域で連携した支援を
地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で尊厳のある生活ができるよう統合的な相談窓口として、権利擁護や地域の支援体制の構築、介護予防の必要な援助などを行います。保健医療の向上、福祉の増進を目的とし、地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関として各市町村に設けられた施設です。
主体運営は市町村と市町村から委託を受けた法人となります。熊本県の運営構成を見てみると、行政が27%、社会福祉協議会が22%、医療法人が20%、社会福祉法人が24%、その他7%となっています。各施設には保健師または看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置され、総合相談、ケアプランの作成、包括的・継続的ケア体制の構築などの業務を行っています。しかしながら、専門職の確保は年々難しくなっており、人材不足は深刻な課題となっています。安定した支援体制を維持するためにも、人材の確保・育成が急務となっています。
ご存知のように社会は超高齢化が進み生産年齢人口が減少し、さらに高齢者の抱える課題は多様化しており画一的な支援では対応できない状況にあります。特に認知症や独居、老々介護、貧困、外国国籍高齢者など複雑な事例が増加しています。また中間山間地域などを抱える地域が多く、地理的に高齢者が点在して効率的な支援が厳しく、訪問や見守りの負担が大きくなる問題もあります。地域によっては民生委員のなり手不足や地域支援者の高齢化が進み地域での支援が難しく、より同センターへの依存が高まる現状もあります。
厳しい状況ではありますが、地域の特性を生かしながら一人一人の心身の状況、置かれている環境などに柔軟に対応し適切なサービスが受けられるようコーディネイトしていくことが重要と考えています。まずは、地域包括支援センターの役割を皆さんに十分に理解いただき、行政を始め医療・介護・福祉の関連機関と連携を取りながらセンターの充実を図り、地域差を生まない誰もが安心して暮らせる社会を目指していきたいと思います。